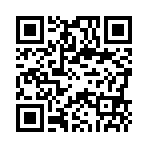RETIOメルマガ11月1日
2019年11月01日
FP・宅建士 金子 at 20:17 | Comments(0) | (財)不動産適正取引推進機構
★☆《令和元年度 宅地建物取引士資格試験の実施》★☆
◇ まず、令和元年台風19号及び低気圧による大雨(10月24日~26日)については、死者90名、行方不明者8名、負傷者447名、住宅全壊600棟、住宅半壊3,123棟(消防庁情報:10月28日6:30現在)となるなど、大惨事となりました。
犠牲となられた方々に心よりお悔やみを申し上げるとともに、被害を受けられた方々には謹んでお見舞い申し上げます。
(なお、台風19号に係る宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等については、
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html
を参照してください。)
◇ さて、去る10月20日(日)には、当機構が都道府県知事の委任を受けて実施している令和元年度の宅地建物取引士資格試験が、全国で実施されました。当機構が発表した速報版によると、全国で、276,019名の申込者のうち、220,694 名が受験しました。申込者、受験者とも、昨年度より、増加となっています。
受験された方々、各会場で設営に携われた方々におかれては、大変お疲れ様でした。
なお、合格発表は、12月 4日(水)です。
(参考:http://www.retio.or.jp/exam/pdf/uketuke_jokyo.pdf )
◇ 一方、行政の動きについては、去る10月18日(金)に、国土交通省の社会資本整備審議会の住宅宅地分科会に、マンション政策小委員会(委員長:齊藤広子 横浜市立大学国際教養学部教授)が設置され、審議が開始されました。
本委員会は、我が国におけるマンションの現状(約655万戸、国民の1 割以上が居住)や、高経年マンションが急速に増加する見通し等を踏まえ、マンションの維持管理の適正化や再生の円滑化に向けた取組みの強化等、マンション政策のあり方を検討するものです。
不動産の適正取引を図る観点からも、マンションの維持管理、再生は大きな課題であり、今後の審議を注目していきたいと思います。
(参考: http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyon01.html)
◇ また、国土交通省の国土審議会の土地政策分科会の企画部会で7月から始まった審議が佳境を迎えています。
本審議は、バブル期に制定された土地基本法の改正と、人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定について検討を行っているものです。
不動産の適正取引を図る上で、土地政策は一つの重要な基盤となるものであり、今後の審議を注目していきたいと思います。
(参考: http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html)
◇ 今年は、夏から先月にかけて、台風、豪雨等の異常気象に見舞われましたが、11月に入ろうとする頃になると、涼しさも増し、本格的な秋の深まりを感じるようになってきました。
11月も、皇位継承の重要行事が予定されていますが、秋らしい穏やかな気候が続いてほしいものです。
ちなみに、今年の紅葉の見通しについては、全国各地で見ごろは遅め、とのことです。
(参考:https://www.jwa.or.jp/news/2019/10/8439/ )
◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆
★☆《平成30年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果 》★☆
国土交通省は、9月30日、平成30年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣及び都道府県知事による免許及び監督処分の実施状況についてとりまとめて公表しました。
1.宅地建物取引業者の状況
平成31年3月末(平成30年度末)現在での宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,569業者、知事免許が121,882業者で、全体で124,451業者。
対前年度比では、大臣免許が64業者(2.6%)、知事免許が605業者(0.5%)それぞれ増加。全体では669業者(0.5%)増加し、5年連続の増加。
2.監督処分等の実施状況
平成30年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおり。
(1)免許取消処分 125件(-21件、14.4%減)
(2)業務停止処分 31件( -5件、13.9%減)
(3)指示処分 26件( -1件、 3.7%減)
(4)合計 182件(-27件、12.9%減)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000196.html
★☆《「全国版空き家・空き地バンク」の機能拡充 》★☆
全国の空き家等の情報を簡単に検索できる『全国版空き家・空き地バンク』について、国有財産を検索できる機能等を追加し、10月1日(火)より運営を開始しました。
これにより、国有財産の取引の更なる円滑化が期待されます。(10月23日公表)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000197.html
◆◇◆ 最近の判例から ◆◇◆
[ 売買契約の違約解除]
宅建業者である買主には売主が抵当権抹消できるかどうか確認する義務がある、などとしたマンションの売主の主張を採用せず、買主宅建業者の売買契約の解除及び売主に対する違約金請求を認めた事例(東京地裁 平成29年7月18日判決 認容 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
宅建業者Xは、平成28年2月24日、Yとの間でYが所有する投資用マンション一室を1200万円で買受ける売買契約を締結し、XがYに手付金10万円を契約日に支払った。また、Yは、同年5月31日に、残金1190万円を受領次第、所有権移転登記の申請手続をするものとされた。
本件売買契約書では、以下の内容が定められている。
⑴抵当権の抹消等(7条)
売主は、本件建物の所有権移転の時期までに、その責任と負担において、本件建物上に存する抵当権等の担保権等、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
⑵契約違反による解除・違約金(13条)
売主又は買主が本件契約上の債務を履行しない時は、相手方は、催告の上、本件契約を解除することができる。売主の違約により買主が本件契約を解除した場合、売主は、買主に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払うとともに、受領済みの金員を返還する。
Yは、本件売買契約後、ローンの抵当権者である銀行に、本物件売却代金をローン残債務に返済することを条件に抵当権解除を申し入れたが、残債務と返済額の差が大き過ぎるとして同意を得られなかった。
5月24日、Yは、Xに対し、本物件の抵当権者である銀行が抵当権の抹消に応じないため、錯誤により本件契約は無効であるとした通知書を送付した。
これに対して、Xは、5月31日までに所有権移転登記手続をしない場合は、契約を解除し、Yは、Xに対し、違約金240万円及び受領済みの手付金10万円を支払うべき旨を通知したが、5月31日、Yは、Xに通知することなく本物件をXとの売買価格より高値で第三者に売却した。
Xは、本件契約を解除したとして、Yに対して、本件違約金条項に基づく違約金240万円と支払済の手付金10万円の計250万円の支払を求めて提訴した。
2 判決の要旨
裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を全額認容した。
(本件違約条項の効力の有無)
⑴ Yは、XがYに宅建士の記名捺印のある37条書面を交付しなかったことから、本件違約条項の効力はないと主張するが、
ア)Xは、37条書面の交付を予定していたが、Yが契約の履行を拒絶したため、その交付をしなかったこと
イ)本件契約書には宅建業法37条の定める内容(本件違約条項を含む。)が記載されて おり、Yは本件違約条項を確認していること
等が認められるから、本件契約書に宅建士の記名押印がないことを理由に、本件違約条項 の効力が否定されることはない。
⑵ Yは、XがYに重要事項説明書を交付しなかったことを根拠として、XがYに対して違約金についての説明をしておらず、本件違約条項の効力はない旨主張する。しかし、宅建業 法35条は、売主が宅建業者である場合に買主に対して重要事項説明書の交付義務を負う 旨定めるのみである。また、XがYに対して本件違約条項について不実を告知したともい えず、同法47条違反の主張も理由がない。
⑶ Yは、Xは宅建業者であるから、Yとの契約前に抵当権の存在と内容を調査し、抵当権者である銀行に抵当権を抹消できるかどうかを確認し、抹消の条件を伝えた上で本件契約をすべきであったのに、この義務を怠ったから、本件違約条項は効力がないとも主張する。しかし、XはYに対し、抵当権が設定されていることを説明しているし、Xが宅建業者であるからといって相手方の取引先の金融機関に対して問合せを行う義務を当然に負うとはい えない。
(停止条件又は解除条件の合意の有無)
Yは、XとYの間には、本件契約について、銀行が抵当権抹消を承諾することを停止条件とする合意、又は、銀行が抵当権抹消を承諾しないことを解除条件とする合意があった旨主張する。しかし、Y自身、抵当権者が抹消に応じないことは想定していなかったと供述しており、銀行が抵当権の抹消に応じなかった場合についての条件をXとの間で合意していたことは考え難い上、本件契約書には、売主が本件建物の所有権移転時期までに負担を消除することが明記されており、Yが、自分の資金と親の支援で住宅ローン債務を完済し、本件建物の抵当権を抹消する旨述べていたことからすると、その主張は採用できない。
(結論)
よって、Xによる契約の解除並びに違約条項は有効であり、Yは、違約金240万円及び受領済みの手付金10万円の支払義務を負う。
3 まとめ
Xが契約無効の主張の根拠とする、宅建士の記名押印のある37条書面未交付については、それが事実であるとしても宅建業法に基づく行政上の処分是非の問題にとどまり、それ自体で民事上の契約無効や損害賠償責任の問題になるものではありません。
また、買主業者の売主に対する重要事項説明・重要事項説明書交付義務がないことは、宅建業法35条1項がその説明対象を「その者が取得し、又は借りようとしている宅地または建物」としており、条文上も明らかです。
抵当権抹消可否に関しては、売主が売買契約の前に銀行に確認すべきものではありますが、もし抹消ができなければ売買契約の履行が不可能となることから、不動産売買に不慣れな個人に対しては、トラブルの未然防止という観点で、宅建業者としては売買契約前に銀行へ確認することをアドバイスしておくべきでしょう。
(RETIOメルマガ第156号より)
◇ まず、令和元年台風19号及び低気圧による大雨(10月24日~26日)については、死者90名、行方不明者8名、負傷者447名、住宅全壊600棟、住宅半壊3,123棟(消防庁情報:10月28日6:30現在)となるなど、大惨事となりました。
犠牲となられた方々に心よりお悔やみを申し上げるとともに、被害を受けられた方々には謹んでお見舞い申し上げます。
(なお、台風19号に係る宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等については、
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo13_hh_000651.html
を参照してください。)
◇ さて、去る10月20日(日)には、当機構が都道府県知事の委任を受けて実施している令和元年度の宅地建物取引士資格試験が、全国で実施されました。当機構が発表した速報版によると、全国で、276,019名の申込者のうち、220,694 名が受験しました。申込者、受験者とも、昨年度より、増加となっています。
受験された方々、各会場で設営に携われた方々におかれては、大変お疲れ様でした。
なお、合格発表は、12月 4日(水)です。
(参考:http://www.retio.or.jp/exam/pdf/uketuke_jokyo.pdf )
◇ 一方、行政の動きについては、去る10月18日(金)に、国土交通省の社会資本整備審議会の住宅宅地分科会に、マンション政策小委員会(委員長:齊藤広子 横浜市立大学国際教養学部教授)が設置され、審議が開始されました。
本委員会は、我が国におけるマンションの現状(約655万戸、国民の1 割以上が居住)や、高経年マンションが急速に増加する見通し等を踏まえ、マンションの維持管理の適正化や再生の円滑化に向けた取組みの強化等、マンション政策のあり方を検討するものです。
不動産の適正取引を図る観点からも、マンションの維持管理、再生は大きな課題であり、今後の審議を注目していきたいと思います。
(参考: http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyon01.html)
◇ また、国土交通省の国土審議会の土地政策分科会の企画部会で7月から始まった審議が佳境を迎えています。
本審議は、バブル期に制定された土地基本法の改正と、人口減少社会に対応した「新たな総合的土地政策」の策定について検討を行っているものです。
不動産の適正取引を図る上で、土地政策は一つの重要な基盤となるものであり、今後の審議を注目していきたいと思います。
(参考: http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s103_kikaku01.html)
◇ 今年は、夏から先月にかけて、台風、豪雨等の異常気象に見舞われましたが、11月に入ろうとする頃になると、涼しさも増し、本格的な秋の深まりを感じるようになってきました。
11月も、皇位継承の重要行事が予定されていますが、秋らしい穏やかな気候が続いてほしいものです。
ちなみに、今年の紅葉の見通しについては、全国各地で見ごろは遅め、とのことです。
(参考:https://www.jwa.or.jp/news/2019/10/8439/ )
◆◇◆ 行政の動き ◆◇◆
★☆《平成30年度宅地建物取引業法の施行状況調査結果 》★☆
国土交通省は、9月30日、平成30年度における宅地建物取引業法に基づく国土交通大臣及び都道府県知事による免許及び監督処分の実施状況についてとりまとめて公表しました。
1.宅地建物取引業者の状況
平成31年3月末(平成30年度末)現在での宅地建物取引業者数は、大臣免許が2,569業者、知事免許が121,882業者で、全体で124,451業者。
対前年度比では、大臣免許が64業者(2.6%)、知事免許が605業者(0.5%)それぞれ増加。全体では669業者(0.5%)増加し、5年連続の増加。
2.監督処分等の実施状況
平成30年度において、宅地建物取引業法の規定に基づき国土交通大臣又は都道府県知事が行った宅地建物取引業者に対する監督処分の件数は、以下のとおり。
(1)免許取消処分 125件(-21件、14.4%減)
(2)業務停止処分 31件( -5件、13.9%減)
(3)指示処分 26件( -1件、 3.7%減)
(4)合計 182件(-27件、12.9%減)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000196.html
★☆《「全国版空き家・空き地バンク」の機能拡充 》★☆
全国の空き家等の情報を簡単に検索できる『全国版空き家・空き地バンク』について、国有財産を検索できる機能等を追加し、10月1日(火)より運営を開始しました。
これにより、国有財産の取引の更なる円滑化が期待されます。(10月23日公表)
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000197.html
◆◇◆ 最近の判例から ◆◇◆
[ 売買契約の違約解除]
宅建業者である買主には売主が抵当権抹消できるかどうか確認する義務がある、などとしたマンションの売主の主張を採用せず、買主宅建業者の売買契約の解除及び売主に対する違約金請求を認めた事例(東京地裁 平成29年7月18日判決 認容 ウエストロー・ジャパン)
1 事案の概要
宅建業者Xは、平成28年2月24日、Yとの間でYが所有する投資用マンション一室を1200万円で買受ける売買契約を締結し、XがYに手付金10万円を契約日に支払った。また、Yは、同年5月31日に、残金1190万円を受領次第、所有権移転登記の申請手続をするものとされた。
本件売買契約書では、以下の内容が定められている。
⑴抵当権の抹消等(7条)
売主は、本件建物の所有権移転の時期までに、その責任と負担において、本件建物上に存する抵当権等の担保権等、買主の完全な所有権の行使を阻害する一切の負担を消除する。
⑵契約違反による解除・違約金(13条)
売主又は買主が本件契約上の債務を履行しない時は、相手方は、催告の上、本件契約を解除することができる。売主の違約により買主が本件契約を解除した場合、売主は、買主に対し、違約金として売買代金の20%相当額を支払うとともに、受領済みの金員を返還する。
Yは、本件売買契約後、ローンの抵当権者である銀行に、本物件売却代金をローン残債務に返済することを条件に抵当権解除を申し入れたが、残債務と返済額の差が大き過ぎるとして同意を得られなかった。
5月24日、Yは、Xに対し、本物件の抵当権者である銀行が抵当権の抹消に応じないため、錯誤により本件契約は無効であるとした通知書を送付した。
これに対して、Xは、5月31日までに所有権移転登記手続をしない場合は、契約を解除し、Yは、Xに対し、違約金240万円及び受領済みの手付金10万円を支払うべき旨を通知したが、5月31日、Yは、Xに通知することなく本物件をXとの売買価格より高値で第三者に売却した。
Xは、本件契約を解除したとして、Yに対して、本件違約金条項に基づく違約金240万円と支払済の手付金10万円の計250万円の支払を求めて提訴した。
2 判決の要旨
裁判所は、次のとおり判示し、Xの請求を全額認容した。
(本件違約条項の効力の有無)
⑴ Yは、XがYに宅建士の記名捺印のある37条書面を交付しなかったことから、本件違約条項の効力はないと主張するが、
ア)Xは、37条書面の交付を予定していたが、Yが契約の履行を拒絶したため、その交付をしなかったこと
イ)本件契約書には宅建業法37条の定める内容(本件違約条項を含む。)が記載されて おり、Yは本件違約条項を確認していること
等が認められるから、本件契約書に宅建士の記名押印がないことを理由に、本件違約条項 の効力が否定されることはない。
⑵ Yは、XがYに重要事項説明書を交付しなかったことを根拠として、XがYに対して違約金についての説明をしておらず、本件違約条項の効力はない旨主張する。しかし、宅建業 法35条は、売主が宅建業者である場合に買主に対して重要事項説明書の交付義務を負う 旨定めるのみである。また、XがYに対して本件違約条項について不実を告知したともい えず、同法47条違反の主張も理由がない。
⑶ Yは、Xは宅建業者であるから、Yとの契約前に抵当権の存在と内容を調査し、抵当権者である銀行に抵当権を抹消できるかどうかを確認し、抹消の条件を伝えた上で本件契約をすべきであったのに、この義務を怠ったから、本件違約条項は効力がないとも主張する。しかし、XはYに対し、抵当権が設定されていることを説明しているし、Xが宅建業者であるからといって相手方の取引先の金融機関に対して問合せを行う義務を当然に負うとはい えない。
(停止条件又は解除条件の合意の有無)
Yは、XとYの間には、本件契約について、銀行が抵当権抹消を承諾することを停止条件とする合意、又は、銀行が抵当権抹消を承諾しないことを解除条件とする合意があった旨主張する。しかし、Y自身、抵当権者が抹消に応じないことは想定していなかったと供述しており、銀行が抵当権の抹消に応じなかった場合についての条件をXとの間で合意していたことは考え難い上、本件契約書には、売主が本件建物の所有権移転時期までに負担を消除することが明記されており、Yが、自分の資金と親の支援で住宅ローン債務を完済し、本件建物の抵当権を抹消する旨述べていたことからすると、その主張は採用できない。
(結論)
よって、Xによる契約の解除並びに違約条項は有効であり、Yは、違約金240万円及び受領済みの手付金10万円の支払義務を負う。
3 まとめ
Xが契約無効の主張の根拠とする、宅建士の記名押印のある37条書面未交付については、それが事実であるとしても宅建業法に基づく行政上の処分是非の問題にとどまり、それ自体で民事上の契約無効や損害賠償責任の問題になるものではありません。
また、買主業者の売主に対する重要事項説明・重要事項説明書交付義務がないことは、宅建業法35条1項がその説明対象を「その者が取得し、又は借りようとしている宅地または建物」としており、条文上も明らかです。
抵当権抹消可否に関しては、売主が売買契約の前に銀行に確認すべきものではありますが、もし抹消ができなければ売買契約の履行が不可能となることから、不動産売買に不慣れな個人に対しては、トラブルの未然防止という観点で、宅建業者としては売買契約前に銀行へ確認することをアドバイスしておくべきでしょう。
(RETIOメルマガ第156号より)